本会議資料は、社会保障審議会医療部会(令和7年10月27日開催)に提出されたものであり、令和8年度診療報酬改定に向けた主要な論点や、医療法人の最新の経営状況(2024年度速報版)が示されています。生成AI(NotebookLM)を使用して要点を整理しました。
引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65278.html
令和8年度診療報酬改定に向けた主要な論点と政策的な含意
| No. | 主要な論点・今後の検討方向 | 政策的な含意(何が動きそうか/何が変わりそうか) |
|---|---|---|
| 1 | 物価高騰・賃金上昇への対応と医療機関の経営安定化 | 医療費の本体改定率(ベースの点数)が大きく引き上げられ、特に病院(平均事業利益率がマイナス)などの厳しい経営状況にある医療提供者への手当が強化されます。 |
| 2 | 医療従事者の人材確保と働き方改革の推進 | 看護職員、歯科衛生士、事務職員など幅広い職種に対して、他産業並みの賃上げを可能にするための新たな評価や、タスク・シフト/シェアを促す人員配置基準の緩和が検討されます。 |
| 3 | 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進 | 電子カルテ情報共有サービスや電子処方箋の普及を後押しするため、システム導入・運用コストに対する評価が新設または拡充され、デジタル化が進んでいない医療機関へのインセンティブが強化されます。 |
| 4 | 医療機能の分化・連携の加速と地域包括ケアシステムの深化 | 高齢者救急(急性期)を受け入れる機能(「包括期機能」として再定義される方向)や、かかりつけ医機能について、要件や施設基準がより厳格な「実績評価」ベースに転換され、役割分担が進みます。 |
| 5 | 医薬品の適正化と医療保険制度の持続可能性の確保 | 長期収載品(特許切れの先発医薬品)の保険給付のあり方やOTC類似薬(市販薬と類似の成分を持つ薬剤)の保険適用除外について議論が進み、保険財政の効率化を目的とした支出抑制策が実行に移されます。 |
各論点の詳細な解説
1. 物価高騰・賃金上昇への対応と医療機関の経営安定化
医療機関の経営状況は極めて厳しいことが報告されています。特に「病院のみ運営法人」の平均事業収益対事業利益率はマイナス0.9%(中央値はマイナス1.3%)であり、本業で赤字となっている法人の割合は58.7%に上ります。
この危機的な状況を踏まえ、令和8年度の診療報酬改定では、光熱水費や委託費、食材料費を含む物価高騰への対応が重点項目とされます。また、人事院勧告に見合う賃上げ(令和7年は3.62%)を民間医療機関でも実現できるような仕組みを報酬に組み込む必要性が強く主張されています。
2. 医療従事者の人材確保と働き方改革の推進
人材確保と業務負担軽減は喫緊の課題であり、医療・福祉従事者の賃金を他産業並みに引き上げることが必要とされています。具体的には、ベースアップ評価料(賃上げのための加算)の引き上げや対象職種の拡大、事務負担の軽減策が検討されます。
業務効率化のため、タスクシフト・シェア(業務の分担・移譲)やチーム医療、ICT(情報通信技術)の活用推進が求められています。また、歯科分野においては、他職種に比べて給与水準が低いとされる歯科衛生士や歯科技工士の離職防止と人材確保策が特に重要視されています。
3. 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
医療DXは、将来的に効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための不可欠な要素です。特に、電子カルテ・電子処方箋の導入・普及は、医療の効率化や薬剤の重複投与の是正に繋がると期待されています。
2025年12月以降はマイナンバーカードの保険証利用が基本となることが閣議決定されており、これに伴い、医療DX推進体制整備加算などの評価のあり方が見直されます。導入コストや維持費用が経営を圧迫しないよう、予算を含めた支援や、特に高齢医師や地方の医療機関へのインセンティブ付与が検討されます。
4. 医療機能の分化・連携の加速と地域包括ケアシステムの深化
2040年頃を見据え、全ての地域・世代が適切な医療を受けられる体制の構築が目標とされています。このため、医療機関の役割分担を明確化する機能分化がさらに促進されます。
特に、回復期機能(リハビリ等)の再編として、高齢者の急性期患者への医療提供機能を含む「包括期機能」の考え方が導入されます。また、かかりつけ医機能については、これまでの体制整備に対する評価から、実際に地域医療に貢献しているかを測る実績評価への転換が検討されています。リハビリテーション、栄養管理、口腔管理(医歯薬連携)の一体的推進も引き続き重視されます。
5. 医薬品の適正化と医療保険制度の持続可能性の確保
医療保険制度の安定性・持続可能性を向上させるため、効率化・適正化の取り組みが不可欠とされています。
具体的な検討課題として、後発医薬品(ジェネリック)やバイオ後続品の使用促進、長期収載品(特許切れの先発医薬品)の保険給付のあり方の見直し(選定療養の仕組みの活用検討)、そしてOTC類似薬(市販薬と類似の成分)の保険給付のあり方の見直しが挙げられています。これらの適正化策は、患者負担や現場への影響を慎重に議論しつつ、保険料負担の抑制に繋がる方向で検討が進められます。
引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65278.html
本記事はAI(NotebookLM)を使用してまとめております。ファクトチェックは必ず引用元をご確認ください。

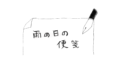

コメント