私は日本の人口減少について、2つの視点から関心を持っている。

1点目は個人の視点である。どういうことかというと、どこに住めば人の数の影響を(ある程度)抑えつつ、幸せに暮らせるかという点である。ある程度の人数がいるエリアの方がよいと思う。人数が少なすぎると店や学校が存続できなくなるからだ。一方で人数が多すぎても幸福ではない。自分の使える空間が非常に狭くなってしまう。今住んでいる東京23区、特に山手線の内側は人が多すぎて息苦しく感じる。ちょうどよいバランスが必要だと思う。今後日本全体で見ると人口は間違いなく減少していく。その減少予測と、自分の空間の割り当ての大きさを考えながら、自分がどこに住むかを決めたいと考えている。
2点目は地域の健康の視点である。もうほとんど臨床薬剤師とは言えないが、それでも医療従事者の端くれである。地域医療・地域保健のサービス維持に危機感を抱いている。どうすれば地域住民の健康を守れるのか。それにはそのエリアにいる人の数、特に健康サービスを多く使う高齢者の人数を考慮することが重要である。地域医療や地域保健のサービスに従事する(私のような)人々の数も考慮しなければならない。
このような考えから、今回はこの本を読んでみた。地方消滅2 加速する少子化と新たな人口ビジョン である。
この手の本はこれで6冊目くらいだが、この本は標準的な一冊として重要だと思う。たとえば「消滅可能性自治体」について。これは若年女性(20-39歳)の人口が2020年から2050年の30年間で50%以上減少する自治体である。全国には744の自治体があるらしい。人口減少の話題ではかならず出てくるワードである(最近は政治家もよく使ったりしている)。女性の人数が次世代の人口を左右する(こどもを産む)ため、若年女性の人数に着目することが人口動態を考える上で重要である。
消滅可能性自治体だけでなく、自治体を分類している本は初めて読んだ。興味深かったので、少しご紹介したい。自治体には大きく分けて「自立持続可能性自治体」「ブラックホール型自治体」「消滅可能性自治体」に分類できる。自立持続可能性自治体とは人口減少率が低く、自治体が持続可能であると予想されている自治体である。ブラックホール型自治体とは、新しく産まれるこどもが減っているが、引っ越してくる人は多い自治体である。消滅可能性自治体とは、新しく産まれるこどもも減っていて、引っ越していく人も多い自治体である。なお、書籍内では「具体的にどうすればよいのか」まで検討されている。
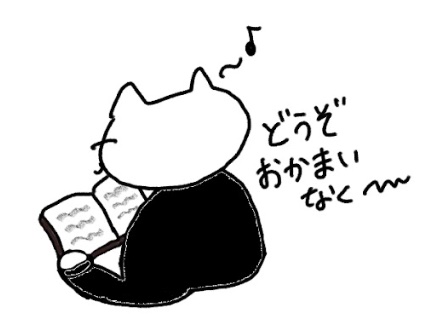
付録として全国自治体の人口予測が掲載されており、興味深い内容だった。私が人口動態の観点から注目した地域は、三大都市圏の中心部である東京23区・横浜市・大阪市・名古屋市、そして地方の主要都市である札幌市・仙台市・広島市・福岡市である。仙台市を除く全ての市にすでに行ったことがある(仙台市は来月行く予定である)。訪れた先では、主に個人の視点の2つ目を重視して見ている(ほかにも交通の便なども考慮しているが)。今のところ私の一位は名古屋市である。人口動態的にも、個人の空間の割り当て的にも、ちょうどよいのである。最近は、東京を離れて名古屋に住みたいという気持ちが強くなっている。

余談だが、食事の美味しさという観点からも各地を見ている。一番美味しかったのは札幌市である。特に白米が非常に美味しく、コンビニのおにぎりやステーキ店のセットのご飯ですら美味しい。水も美味しく、本当に驚いた。他に美味しかったのは福岡市・大阪市・名古屋市である。それぞれが独特の食文化があり、どれも美味しい。こうして比べてみると、東京のご飯はあまり美味しくないと感じる。地方出身で上京した人たちが口を揃えて「東京のご飯は美味しくない」という理由がよくわかる(お金を出せれば美味しいのだが)。
というわけで、今回は私の関心事である「人口」に関連する書籍をご紹介した。人口という観点から地域を見てみるのも、また興味深いと思う。もしよければ、皆さんも試してみてください。
地方消滅2 加速する少子化と新たな人口ビジョン (中公新書)
人口戦略会議 (編集)
記事を書いたのは…
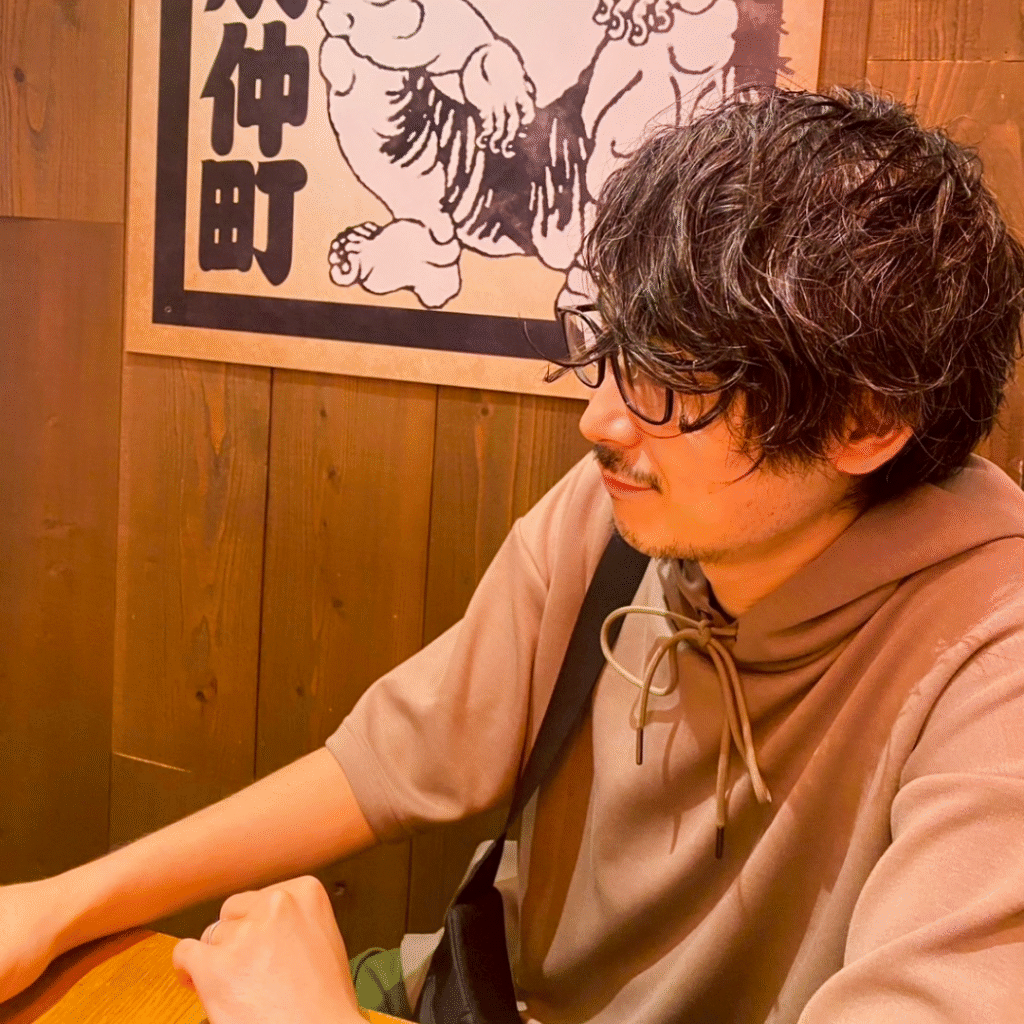
部長(ぶちょう)/ 木内 翔太(きうち しょうた)

職業:フリーランスの自由人。東大院生をしてたり、大学以外で研究してたり。たまに薬剤師してたりもします。
ひとこと
はじめまして。てくてく放送部の部長です。最後までお読みくださりありがとうございます。
忙しい日常の中で「あなたのほっと一息」にご一緒できたらとても嬉しいです。
末永くお付き合いください。
著書はこちらから(もしくは下記画像のBUY ON AMAZONのクリックで該当サイトに飛びます)
※Kindle unlimitedで無料で読むことができます!Kindle unlimited登録はこちらから

ホッと一息つきたい時に、Podcastはいかがですか?
メルマガ「てくてく通信」では、部長のほぼ日連載エッセイ「てくてくと、今日も」をお届けしています!お楽しみに!
てくてく放送部公式LINEスタンプも販売中です!




コメント